キャラクターに命を吹き込む
アニメーターという仕事の喜び
アカデミー賞短編アニメーション映画賞にノミネートされた『ダム・キーパー』、Netflixで人気を集める『ONI〜神々山のおなり』などを手がけ、アメリカを拠点に世界的に活躍するアニメーターの中村俊博さん。実は姉妹校の卒業生です。学生時代に取り組んだこと、そして現在のお仕事について伺いました。

卒業生
中村 俊博氏
TOSHIHIRO NAKAMURA
2003年姉妹校卒業。CGジェネラリストとしてTVコマーシャル、PVなどを手がける。その後、フリーランスとして東映アニメーションやNHKの作品を担当。’10年渡米、サンフランシスコのアカデミー・オブ・アート大学入学。短編アニメーション『ダム・キーパー』を手がけ、元ピクサーの堤大介氏が率いるトンコハウスに合流。現在はゲーム制作なども手がけている。

苦手なアニメーション制作を克服すべくアメリカに飛び込んだ
● 在学中はどんな学生でしたか?またどのように現在のお仕事に辿り着かれましたか?
中村氏 学生時代は、グラフフィックデザイン、モデリング、テクスチャーなど基礎的なことを学びながら、絵を描くこともしていました。当時は24時間開いていた学内のコンピューターラボに篭り、土日も授業がありましたから、基礎学習と作品づくりに没頭する日々を送っていましたね。在学中に、レベルファイブというゲーム制作会社にインターンに行き、卒業後は東京のCMの制作会社に入りました。当時は、実写作品のCGをやってみたいという思いがあったんです。20歳で入社し24歳の頃には、なんとなく映像制作のノウハウが一通りわかってきて、その時に、もう1度学び直したいと、サンフランシスコの美大受験を決めたんです。
● 昔から、海外で働きたいと考えていたのですか?
中村氏 実は違うんです。働きながら、自分はアニメーション以外のことは一通りできるようになったと感じたんです。であれば苦手分野であるアニメーションを勉強しようと。「せっかく大人になってから美大に行くなら、海外に出た方がいい」そう当時の上司にアドバイスをもらい、そこで初めて海外に出ることを考えたんです。そこから学費を稼ぐべく、働きながらも受験勉強、英語の勉強を始めました。その間に『NHK スペシャルドラマ 坂の上の雲』などの作品も担当させてもらいました。当時は仕事と勉強で、寝る間もなかったですね(笑)。そうして結局、大学に入り直したのは28歳の時でした。最初は水も買えないくらいの英語力でしたから苦労はしましたが、在学中に元ピクサーの堤大介監督と出会い、『ダム・キーパー』という作品に関わらせてもらいました。卒業後は、堤さんがご自身のスタジオ「トンコハウス」を立ち上げるので一緒にやらないかと声をかけてくださり、二つ返事でこの道に入ったんです。

● 『ONI〜神々山のおなり』ではアニメーションスーパーバイザーを務められましたが、これはどんなお仕事ですか?
中村氏 トンコハウスには実は僕しかアニメーターがいません。まずキャラクターごとの性格をふまえたテストアニメーションをつくり、アニメーションのスタイルも監督と一緒につくりあげました。またこの作品は日本にいる40名のアニメーターさんたちと共同で制作したのですが、キャラクターの動きや性格など全員が理解できるよう、モデルを共有、さらにクオリティチェックなど、監督と日本のアニメーターさんの橋渡しのような仕事もしました。
● キャラクターの性格や動きはどのように日本と共有したのでしょうか。
中村氏 このキャラクターは、あの映画のあのキャラに似ています、などレファレンス(参考資料)添えて、それぞれのキャラクターを説明した資料をつくりました。監督と僕は同じ場所にいますので、言葉でもなんとなくイメージを共有できますが、離れているスタッフと共有するには、多くのレファレンスが必要です。そういうものをたくさん集めて日本と共有していました。例えば、『ONI』の「なりどん」というキャラのイメージはドリフターズの高木ブーさんと、映画『アイ・アム・サム』のお父さんなのですが、具体的な名前と資料を出すことでみんなのイメージがどんどん具体化していくんです。

「好きでないジャンル」には、自分にないものがある。
そこに成長のチャンスがある。
● アニメーション業界で活躍を目指す学生が、今のうちにしておくべきことはなんだと思いますか?
中村氏 アーティストとして引き出しを多くもつために、たくさんの作品を見てください。それが先ほど言った「あの作品のあのキャラのように」というアイデアにつながります。また監督からそのように指示があった時も、「あのキャラのことか」とすぐ理解できます。そして自分の好きな作品だけではなく、幅広く見ることが大事です。「好きでないジャンル」というのはつまり、そこに自分にないものがある、成長のチャンスがあるということ。仕事になれば、自分の得意分野だけではなくさまざまなオーダーがあるでしょう。それらに対応すべく、自分にないものも、どんどん吸収していってください。私は、アニメーション制作が苦手だったことで、「このまま一生アニメーションを避けていくのか」と思ったら悔しくなりまして(笑)、あえてそこに飛び込みました。もちろん得意分野を伸ばしていくことの方が理にかなってはいますが、みなさんには色々な世界を見てほしいと思います。また英語を学ぶことも大事です。海外に出て行かないにしても、レファレンスを探す際に英語で探せば、日本語だけよりも何倍も多くいいものが見つかります。また『ONI』のように国を跨いで制作するスタイルも増えていくでしょう。視野を広く持つためには、ぜひ英語をしっかり身に付けてください。

学生 アニメーションを制作するうえで、アニメーターにも演技力が必要と聞いたのですが、本当でしょうか?
中村氏 アニメーターは役者でないといけない、ということはよく言われています。他のアニメーターや監督にイメージを伝える際に自分で演じてみせることができますからね。しかし僕は演技が苦手ですので、映画を見て「この役者さんのこの演技がいいな」と思ったら、それを覚えておいてストックしておく。「あの映画のあの人のように」と口で言えるようになる、というやり方でカバーしています。
学生 制作の際、もっとも大事にしていることはなんですか?
中村氏 キャラクターのデザインをしていく際に、「なんとなく」やらないことです。なぜこのポーズを取るのか、なぜこの形なのか、すべてに理由づけをすることを大事にしています。理由があれば、キャラクターは具体的になって、説得力が出るんです。
学生 私は制作は好きですが、自由に作品をつくっていいとなると、戸惑ってしまいます。いい解決方法はありますか?
中村氏 制作において、制限がない完全な自由というのも戸惑ってしまいますよね。制限があることで燃える人も確かにいます。そういう場合は、「これをつくったら」とクラスメイトなどに言ってもらって、あえて制限をつくるのもいいかもしれません。たくさんつくっていけば、本当につくりたいものが見えてきますよ。
学生 アニメーションをつくることの最大の魅力はなんですか?
中村氏 本来存在しないはずのキャラクターに命を吹き込むことが私の仕事です。ですから見た人が、そのキャラクターを見て、笑ったり泣いたりしてくれた時がいちばん嬉しいですね。その瞬間のために、膨大なレファレンスを集めて、緻密に作っていっているんです。みなさんにも将来ぜひその喜びを味わっていただきたいです。
こちらもチェック!
-

Microsoft×SONY
×STUDENTS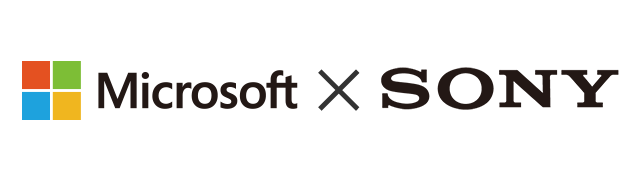
日本マイクロソフト株式会社
技術統括室 エンジニア千葉 慎二氏
ソニー株式会社
インキュベーションセンター
メタバース事業開発部門
シニアビジネスプロデューサー上田 欣典氏
それぞれの視点から未来の可能性を語り合う。
-

Unity×STUDENTS

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
シニア・アドボケイト簗瀨 洋平氏
最先端のリアルタイム3Dプラットフォームで、クリエイターたちの創造性を解放
-

NVIDIA×STUDENTS
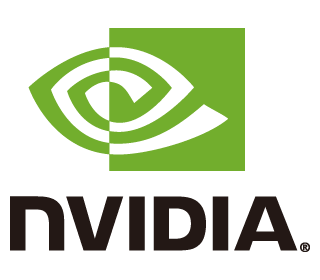
エヌビディア合同会社
エンタープライズ事業本部
vGPUビジネス開発マネージャー後藤 祐一郎氏
仮想GPUの高性能コンピューティングで、あらゆる産業分野にイノベーションを
-

CAPCOM×STUDENTS

株式会社カプコン
CS第二開発統括
開発三部 VFX室當銘 龍司氏
株式会社カプコン
CS第一開発統括
第一ゲーム開発部 第五ゲーム開発室藤木 泰成氏
自分が追い求める表現が完成した時
ゲームづくりの醍醐味と喜びを感じる -

intel×STUDENTS

インテル株式会社
インダストリー事業本部
公共・スマートシティー事業推進部
教育・スマートシティー事業推進マネージャー遠藤 未来氏
プロモーションの基礎はマーケットを知り、データを集めること
-

EPIC×STUDENTS

エピック ゲームズ ジャパン
代表河﨑 高之氏
ゲーム作りはUnreal Engineでさらに自由に!面白いゲームを生み出すために必要なこととは!?
-

TOSHIHIRO NAKAMURA
姉妹校卒業生
アニメーター
中村 俊博氏
キャラクターに命を吹き込むアニメーターという仕事の喜び








